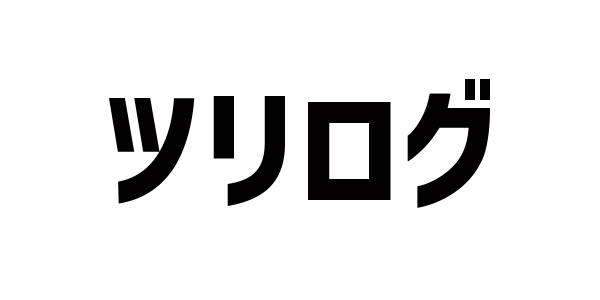釣りを楽しむ人なら一度は聞いたことがある渓流釣りです。ただ、渓流釣りではどんな事をするのだろう?と疑問に思っている人がいるかもしれません。本記事では、初心者の方に向けて渓流釣りの釣り方やコツ、ポイント、装備について紹介します。
渓流釣りとは?楽しみについて

渓流釣りが行われる渓流は川の上流域を示す言葉で、渓流釣りは川の上流域で行われる釣りのことです。渓流には流れに沿って岩や砂利が存在し、急こう配で速い流れといった特徴があり、日本に流れる川の美しさが堪能できます。
また、渓流の周辺には木々が生い茂っている場合があり、森林浴によって心と体をリフレッシュする楽しみもあります。例えば、渓流の周辺にある民宿など宿泊施設に泊まり、早朝から美しい自然の中で釣りをはじめるといった旅行気分で渓流釣りを楽しむこともできます。
渓流で釣れる魚について

渓流で釣れる魚はヤマメやイワナ、アマゴ、ニジマスなどで、とても美しく食べても美味しいので紹介します。
渓流の女王・ヤマメ
サケ目サケ科に属するヤマメは一生を川で過ごす魚です。ヤマメは北海道から九州までの渓流などに生息し、2年間成長を続けても20㎝程度の小さな体です。ヤマメの体には美しい斑紋模様(パーマーク)があり、食べても美味しいことから、渓流の女王と呼ばれています。
ヤマメは比較的冷たい水を好み、24℃になるとエサを食べなくなるといわれているので、渓流釣りでの参考にしてください。ヤマメを釣ったら、内臓を除去して塩焼きにしたり、揚げて酢漬けにしたりして食べると、とても美味しいです。
初心者向けターゲット・アマゴ
サケ目サケ科に属するアマゴは、神奈川県より、西の本州、四国、九州の河川と沿岸に生息するといわれています。ただ、放流によって生息範囲は広がり、色々な場所で釣れるため、初心者向けの魚です。
アマゴはヤマメに似て美しい魚ですが、アマゴには体に散りばめられた鮮やかな朱点があるので区別できます。釣ったアマゴは内臓を除去して塩焼き、天ぷら、甘露煮にして食べると美味しいです。
大型肉食魚・ニジマス
サケ目サケ科サケ亜科タイヘイヨウサケ属のニジマスは外来魚で、主に北海道に生息していていましたが、放流によって日本全国に生息範囲が広がっています。体長は一般的に40㎝程度ですが、80㎝以上もある大型のニジマスもいます。
肉食のニジマスは、朱色の縦帯がある体に散りばめられた小さな黒点が特徴となっています。釣ったニジマスは内臓を除去して、ムニエルやフライにしたり、塩焼きにしたりして食べると美味しいです。
渓流の王様・イワナ
サケ目サケ科イワナ属のイワナは日本の各地で生息しており、多くは一生を淡水で過ごします。イワナは肉食性で、魚やサワガニ、虫、カエルなどを捕食して生活しており、その獰猛さや美しさから渓流の王様といわれ、釣り人が憧れる魚です。
イワナは2年を過ぎると18〜22cm程度に成長し、冬の寒い時期は体が少し黒ずむことがあります。釣れたイワナは内臓を除去して、塩焼きやムニエルにするととても美味しいです。
渓流釣りではどんな釣り方があるの?

渓流釣りでは、ルアーフィッシングやフライフィッシング、テンカラ釣り、エサ釣りといった釣り方が一般的です。これらの釣り方で、ヤマメやイワナ、アマゴ、ニジマスは狙えますので紹介します。
渓流のルアーフィッシング
渓流でルアーフィッシングを行うメリットは、延べ竿やテンカラ竿より遠くにキャスティングできることです。また、渓流で餌を採取する手間や時間がかからないメリットもあります。
渓流のフライフィッシング
渓流でフライフィッシングを行うメリットは、ルアーが使えない浅い水深でも魚を釣ることができます。またルアーフィッシングと同様に渓流で餌を採取する手間や時間がかからないメリットがあります。
渓流のテンカラ釣り
渓流でテンカラ釣りを行うメリットは、釣り場が狭くてルアーフィッシングやフライフィッシングでキャストできなくても釣りができます。また、用意する道具は少なく、主にロッドとライン、毛ばりのみで釣りができるメリットもあります。
渓流のエサ釣り
渓流でエサ釣りを行うメリットは、川底の石の裏などから採取した虫など生餌を使うので、ルアーや毛ばりといった疑似餌に比べ魚に警戒されないことです。またテンカラ釣りと同様に主にロッドとライン、毛ばりのみの釣りなので荷物が少なくてすみます。
初心者のために!渓流釣りに必要な道具や装備

ルアーフィッシングやフライフィッシング、テンカラ釣り、エサ釣りなど渓流釣りに必要な道具や装備について初心者向けに紹介します。
渓流のルアーフィッシングに必要な道具

渓流のルアーフィッシングで使うリールの選び方
リールは構造の違いから、大きくベイトリールとスピニングリールに分けられます。渓流で使うルアーは比較的軽いものが多いことやライントラブルが少ないことから初心者の方にはスピニングリールがおすすめです。
大きさは1500〜2000番で、できるだけ軽く操作感が良いスピニングリールを実際に釣具店で手に取って操作して選んでください。
渓流のルアーフィッシングで使うロッドの選び方
渓流のルアーフィッシングで使うロッドは長さが通常5〜6ftのルアーフィッシング用のロッドを選ぶのが一般的ですが、渓流で釣りをする場合、釣り場の広さに合わせてロッドの長さを決めるのがポイントです。狭い釣り場でキャスティングを想定した場合、短いロッドを選んだ方が、キャスティングしやすいです。
使用するルアーの重さによってロッドを決めるのが一般的で、ロッドの説明書に記載されているルアーの重さを参考にロッドを選んでください。
ただ、渓流のルアーフィッシングで使うルアーは比較的軽いので、UL(ウルトラライト)、L(ライト)、ML(ミディアムライト)といった柔らかいロッドを選ぶのが一般的です。
渓流のルアーフィッシングで使うラインの選び方
渓流のルアーフィッシングで使うルアーは比較的軽いので、メインのラインも軽く細くても強いPEライン(0.6号程度)がおすすめです。PEラインとルアーの間にはPEラインの4倍くらいの太さで1m程度のフロロカーボンのライン(ショックリーダー)を結ぶことで、PEラインの弱点である根ずれのトラブルなどを防ぐことができます。
PEラインは高価なので安価なナイロンを選ぶ事もできますが、ショックリーダーは必要ありません。
渓流のルアーフィッシングで使うルアーの選び方
渓流のルアーフィッシングで使うルアーは、ミノーとスプーンを用意してください。
ミノーは小魚のような形をしており、先端にリップが付いているルアーです。渓流でヤマメやイワナ、アマゴなどを狙う場合は、ミノーの中でも水面付近を泳ぐフローティングミノーと水の中に沈んで泳ぐシンキングミノーを用意してください。これらのミノーのサイズは3〜5㎝、色はオレンジ系、グリーン系、シルバー系がおすすめです。
また、ミノーで魚の反応が悪かったり、ニジマスをメインに狙ったりする場合は、金属製のスプーンと呼ばれるルアーも用意してください。スプーンはミノーと同じでサイズは3〜5㎝、色は、オレンジ系、グリーン系、シルバー系がおすすめです。
渓流のフライフィッシングに必要な道具

渓流のフライフィッシングで使うリールの選び方
フライフィッシングで使うリールはフライリールと言われ、フライフィッシング専用のリールです。フライリールを選ぶ時は、使用するフライラインやロッドに合わせるのが一般的で、それぞれの道具に番手(#(番))が設定されています。
例えば、渓流のフライフィッシングで使うリールを選ぶ際は、ロッドやフライラインは#3(3番)がおすすめで、#2〜3(2〜3番)のキャパシティがあるフライリールがマッチします。
また、同じ番手のフライリールでも、スプールの横幅が狭いナロースプールで、内径が小さいミッドアーバーのフライリールを選んだ方が持ち運びに便利なので、渓流のフライフィッシングに向いています。
渓流のフライフィッシングで使うロッドの選び方
フライフィッシングで使うロッドは、フライフィッシング専用のロッドを選びます。フライフィッシング専用のロッドを選ぶ時は、フライリールと同様に使用するフライラインに合わせるのが一般的で、それぞれの道具に番手(#(番))が設定されています。
例えば、渓流のフライフィッシングで使うロッドを選ぶ際は、フライラインが#3(3番)がおすすめで、#3(3番)のロッドのほうがマッチします。
また、渓流で使うロッドの場合、7ft以下の短いロッドが扱いやすく、初心者の方におすすめです。
渓流のフライフィッシングで使うラインの選び方
フライフィッシングで使うラインはフライラインと呼ばれることがあり、フライフィッシング専用のラインとなっており、番手(#(番))が設定されています。渓流のフライフィッシングで使うフライラインは#3(3番)がおすすめで、同じ番数でも、浅瀬に適しているフローティングタイプで、狙いが定まりやすいダブルテーパーのフライラインが渓流のフライフィッシングにマッチします。
フライリールにフライラインを直接巻き始めるのではなく、最初に下巻きとしてバッキングライン(20lb程度)を巻いてからフライラインと結んで、巻き終わったフライラインの先にリーダー(太さ:7X~5X、長さ:7.5ft程度)を結びつけます。バッキングラインの長さはフライリールに表示されています。
渓流のフライフィッシングで使う仕掛けの選び方
フライフィッシングで使う毛ばりは昆虫などに似せた疑似餌です。例えば、渓流のフライフィッシングで#3(3番)のロッドがおすすめで、毛バリのサイズは#20~#8(20番〜8番)を選んでください。毛バリのサイズは数値が小さくなればなるほど大きくなります。
毛バリを選ぶ際はサイズの他に、ウェットと呼ばれる水に沈む毛バリとドライと呼ばれる水に浮く毛バリがあるので、両方用意したほうがいいです。ウェットにはヘアズイヤー、ドライにはエルクヘアカディスやパラシュートといった毛バリがあります。
渓流のテンカラ釣りに必要な道具

渓流のテンカラ釣りで使うロッドの選び方
渓流のテンカラ釣りに必要なロッドは、テンカラ竿と呼ばれることがあるテンカラ釣り専用のロッドを選んでください。テンカラ竿の長さは2.7〜4mが一般的ですが、渓流で釣り場が狭い場合は短いものを選んだほうが扱いやすいです。
渓流のテンカラ釣りで使うラインの選び方
テンカラ釣りで使うラインはテンカラ釣り専用のラインとなっており、テーパーラインとレベルラインの2種類があります。テーパーラインは、ナイロン糸など編み込んで1つにしたラインですが、強く引っ張るとヨリが緩んでしまいヨレヨレになるのであまり使われなくなりました。
一方、レベルラインにはフロロカーボンを使っており、適度に重いので毛バリを飛ばしやすくおすすめです。レベルラインの太さは3号を目安に選んでください。レベルラインと毛バリの間にはハリスと呼ばれるラインを結びつけます。ハリスはナイロンやフロロカーボンのラインを使いますが、太さは0.8号、長さは1m程度を目安にしてください。
渓流のテンカラ釣りで使う仕掛けの選び方
テンカラ釣りでは逆さ毛バリと普通毛バリが使われますが、大きさ#18~#10を目安にしてください。フライフィッシングで使われる毛バリを流用することもあります。
渓流のエサ釣りに必要な道具

渓流のエサ釣りで使うロッドの選び方
渓流のエサ釣りで使うロッドは、渓流竿と呼ばれる渓流専用のロッドもありますが、手持ちの延べ竿でも代用できることがあります。渓流竿の長さは川幅に合わせて選ぶ必要があり、4〜7mが一般的です。
重さは軽ければ軽いほど腕の疲労が少なく、仕舞寸法が50㎝前後だと持ち運びに便利です。
渓流のエサ釣りで使うラインの選び方
仕掛けに使うラインは、水中に入らない上部を構成する天井イト、次に水に沈む水中イト、ハリに結ぶハリスに分かれています。天井イトはナイロンで太さは0.4〜0.6号、水中イトはナイロンかフロロカーボンで太さは0.2〜0.3号、ハリスの太さは水中イトより少し細いものを選ぶのが一般的です。
渓流のエサ釣りで使う仕掛け・エサの選び方
渓流のエサ釣りで使う仕掛けには、仕掛けを流している場所や魚のアタリを確認する目印、仕掛けをコントロールするおもり、ハリがあります。目印はオレンジ、ピンク、グリーンなど蛍光色のヤーンがおすすめです。
おもりはガン玉(3号〜4B)、ハリは使うエサが小さな川虫であれば1〜4号、ミミズやブドウ虫であれば5〜7号を目安に選ぶのがポイントです。
エサについては、釣具店などで用意するのはイクラやミミズ、ブドウ虫です。更に、川底の石をひっくり返して流れ出た川虫をタモですくって使います。
渓流釣りで用意したい装備について

渓流釣りで用意したい装備にはシューズ、ウエイダー、アングラーベストに加え、紫外線を防ぐ帽子やサングラス、手を守るグローブ、荷物を運ぶバックパック、ランディングネット、タックルボックスなどがあります。ライフジャケットはどんな釣りでも用意して着用してください。
シューズには濡れた岩などにグリップ力を発揮するラバーソールや、ぬめりのある水垢やコケにグリップ力を発揮するフェルトソールを使ったタイプがあるので、釣り場の状況によって選ぶのがポイントです。
ウエイダーを履けば、足や下半身を濡らすことなく川に入れます。チェストハイウエイダーは胸の高さまでカバーするのでおすすめの装備です。
渓流のルアーフィッシングで釣り方のコツやポイント

渓流のルアーフィッシングでは、上流に進みながら釣りをするのが一般的です。自分の斜め上流へキャスティングすることで、魚と一定の距離を取りながらアピールするのがコツです。
例えば、上流に魚がいそうな水深のある淵や波立ちがある瀬や落ち込みを見つけたら、キャスティングするのがポイントです。
渓流のフライフィッシングで釣り方のコツやポイント

渓流のフライフィッシングでも他の釣り方と同様に自分の斜め上流へキャスティングすることは同じで、上流に魚がいそうな水深のある淵や波立ちがある瀬や落ち込みを見つけたら、キャスティングするのがコツです。
ただ、フライフィッシングの場合、キャストした後、先行して流れるラインにドライフライが引っ張られて川の流れの速度より速く流れてしまうことがあるので、ドライフライを川の流れと同じような速度で流すナチュラルドリフトの方が魚の反応は良いです。対策として、ロッドを跳ね上げて上流側に倒すことで、ラインを先行させることを防ぎます。
渓流のテンカラ釣りで釣り方のコツやポイント

渓流のテンカラ釣りでは他の釣り方と同様に自分の斜め上流へキャスティングすることは同じで、上流に魚がいそうな水深のある淵や波立ちがある瀬や落ち込みを見つけたら、キャスティングするのがコツです。
テンカラ釣りでは、季節によって毛バリの大きさを変えて魚の反応を観察しながら釣るのがコツです。
例:3月初旬は#20程度の小さな毛バリ、暖かくなるにつれ#16番くらいの毛バリを試してください。4月下旬から#14へ移行し、状況によっては#12を使っても魚の反応が良いこともあります。5月中旬から6月までは#10~#14をメインに試してください。7月以降は#12以上がおすすめです。
渓流のエサ釣りで釣り方のコツやポイント

渓流のエサ釣りでは、他の釣り方と同様に自分の斜め上流へキャスティングすることは同じで、上流に魚がいそうな水深のある淵や波立ちがある瀬や落ち込みを見つけたら、キャスティングするのがコツです。
エサ釣りではおもりで調整して、川の流れの速さより少し遅い速さで仕掛けを流して、生餌をしっかり魚に見せてください。また、生餌は川底をはうように調整して流すのがコツです。
初心者の渓流釣りのマナーについて

渓流では釣りができる時期は決まっており、遊漁券を買う必要がありますので、釣りをしようと考えている渓流を管理している漁協に問い合わせてください。渓流では上流に向かってキャスティングすることが多いので、上流にいる他の釣り人とは十分に距離をとるのがマナーです。
他の釣りと同様、釣りで出たゴミは持ち帰るのがマナーです。
まとめ

渓流釣りについて紹介しましたが、都会に住んでいる釣り人にとっては、渓流釣りは敷居が高いというイメージがあるかもしれません。旅行やキャンプを兼ねての渓流釣りを楽しむのもおすすめなので、一度はチャレンジしてみませんか?