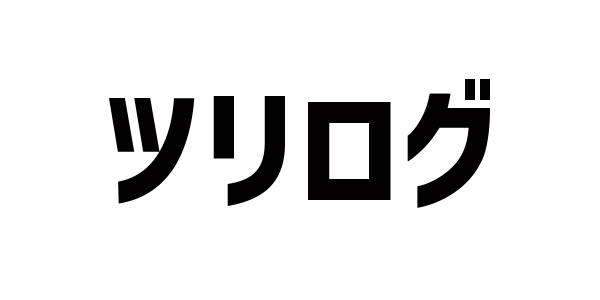はじめに:友釣りで鮎を釣ってみよう!
夏の風物詩といえば、清流を優雅に泳ぐ「鮎(アユ)」。そして、その鮎を釣る伝統的な釣り方として「友釣り」があります。友釣りは、生きた鮎(オトリ鮎)の習性を利用して、縄張りに入ってきた別の鮎を「野鮎」として引っ掛けて釣る、非常に奥深く、そして熱い釣りです。
「友釣り」と聞くと、「難しそう」「道具が高そう」といったイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、基本をしっかり押さえれば、初心者の方でも十分に楽しめます。この記事では、鮎の友釣りをこれから始めてみたい!という方のために、友釣りの基本的な仕組みから必要な道具、仕掛け、そして釣り方のコツまで、ゼロから丁寧に解説していきます。
この記事を読めば、あなたも清流で鮎と真剣勝負を繰り広げ、あの独特な「ガツン!」という衝撃と、引きの強さを味わうことができるでしょう!さあ、友釣りの世界へ飛び込んでみましょう!
鮎の友釣りとは?その魅力と基本的な仕組み

友釣りは、鮎が持つ「縄張り意識」という習性を利用した独特な釣り方です。まずは、その魅力と基本的な仕組みを理解しましょう。
1. 友釣りの魅力
友釣りには、他の釣りにはない独特な魅力が詰まっています。
- 鮎との知恵比べ: 縄張りを持つ鮎(野鮎)が、自分の縄張りに侵入してきたオトリ鮎を追い払おうと体当たりする習性を利用します。この心理戦が友釣りの醍醐味です。いかに野鮎のテリトリーにオトリ鮎を誘導し、縄張り意識を刺激するかが腕の見せ所となります。
- 強烈な引きと独特な感触: 友釣りで掛かる鮎は、基本的に縄張りを持つ元気な鮎です。掛かった瞬間の「ガツン!」という強烈なアタリと、竿を通して伝わる鮎の生命力あふれる引きは、一度味わうと忘れられません。特に、良型の鮎が掛かった時の引きはまさに圧巻です。
- 自然との一体感: 清らかな渓流に立ち込み、水中のオトリ鮎の動きを読みながら、自然の息吹を感じられます。川の流れ、風、日差し、そして鮎の動き。五感をフル活用し、自然と一体となって釣りをする感覚は、友釣りならではの魅力です。
- 釣趣の奥深さ: 竿の操作、糸の張り具合、オトリ鮎の泳がせ方、ポイントの見極めなど、さまざまな要素が釣果に直結します。試行錯誤を繰り返し、技術を磨くことで、釣果が大きく変わるため、常に上達を実感できる奥深さがあります。
2. 友釣りの基本的な仕組み
友釣りは、大きく分けて以下のステップで進行します。
- オトリ鮎の準備: 釣具店などで購入した「オトリ鮎」と呼ばれる生きた鮎を用意します。このオトリ鮎に、後述する友釣り仕掛け(鼻カン、逆さ針など)を装着します。
- オトリ鮎の泳がせ: オトリ鮎を川に放ち、竿で操作しながら泳がせます。オトリ鮎は、ハナカンと呼ばれる金具を鼻に通されているため、泳ぎをコントロールしやすいようになっています。
- 野鮎の縄張りへの侵入: オトリ鮎を、縄張りを持つ元気な野鮎(天然鮎や育ちの良い鮎)がいると思われるポイントへ誘導します。野鮎は、自分の縄張りに侵入してきたオトリ鮎を排除しようと、体当たりを仕掛けてきます。
- 「追い」と「掛け」: 野鮎がオトリ鮎に体当たりした際に、オトリ鮎のお尻付近に付けられた「掛け針(錨針など)」が野鮎に引っ掛かります。これが「掛かる」瞬間です。
- 取り込み: 掛かった野鮎が暴れるのを竿でいなし、竿の弾力を利用しながら手元まで引き寄せ、タモ網で慎重に取り込みます。
- 新しいオトリ鮎に: 取り込んだ野鮎は、元気であれば次のオトリ鮎として使用できます。こうして、次々と鮎を釣り上げていきます。
この一連の流れが友釣りの基本的な仕組みです。いかにオトリ鮎を自然に泳がせ、野鮎の活性を刺激するかが釣果を左右します。
鮎の友釣りに必要な道具を揃えよう!

友釣りを始めるには、いくつかの専用の道具が必要です。ここでは、初心者の方が必要最低限揃えるべき道具と、それぞれの役割を解説します。
1. 鮎竿(アユザオ)
友釣りの核となる道具です。鮎竿は、その特性上、非常に長く、軽量で、かつ強度と粘りを兼ね備えているのが特徴です。
- 長さ: 主に7mから10m程度が一般的ですが、初心者には操作しやすい7mから8m程度のものがおすすめです。長い竿ほど遠くのポイントを狙えますが、操作が難しくなります。
- 調子(ちょうし): 竿の曲がり方や硬さを示すものです。「先調子」「胴調子」などがありますが、最初はオールマイティに使える中間的な調子の竿が良いでしょう。
- 選び方のポイント: 軽量で持ちやすく、ある程度の強度があるものを選びましょう。高価なものから手頃なものまでさまざまですが、最初は釣具店の店員さんに相談して、初心者向けのモデルを選ぶのが賢明です。中古品も選択肢の一つですが、状態をしっかり確認しましょう。
2. 友釣り仕掛け(完成品)
友釣り仕掛けは、鮎を掛けるための重要なパーツです。最初は完成品を購入するのが手軽で確実です。
- 天上糸(てんじょういと): 竿の先に結ぶ一番上の糸。ナイロンやフロロカーボン製が一般的です。竿の長さや川の状況に合わせて調整します。
- 水中糸(すいちゅういと): 天上糸と中ハリスをつなぐ、水中に沈む部分の糸。細い複合メタルラインやフロロカーボンラインが主流です。鮎の動きを伝える重要な役割を持ちます。
- 中ハリス(なかハリス): 水中糸と鼻カン仕掛けをつなぐ糸。
- 鼻カン(ハナカン): オトリ鮎の鼻に通す金属製の輪。オトリ鮎をコントロールする役割があります。
- 逆さ針(さかさばり): オトリ鮎の尻ビレ付近に刺し、鼻カンから伸びるハリスを固定するための針。
- 掛け針(かけばり): 鮎を掛けるための針。一般的に「錨針(いかりばり)」と呼ばれる3本〜4本針が主流です。針の種類や号数は、鮎の大きさや掛けるポイントによって使い分けますが、最初は一般的なサイズのものを数種類用意しておくと良いでしょう。
これらのパーツがセットになった「鮎友釣り仕掛けセット」が釣具店で販売されているので、最初はそれを選ぶと間違いありません。
3. タモ網(玉網)
釣った鮎をすくい取るための網。
- 形状: 一般的に「抜きダモ」と呼ばれる、柄が短く、網が小さいものが友釣りでは使われます。
- 網の素材: 鮎のヌメリを取らず、魚体を傷つけにくい素材(ナイロンモノフィラメントなど)が使われています。
4. 舟(フネ)
釣った鮎やオトリ鮎を入れておくための容器。
- オトリ缶(オトリカン): オトリ鮎を活かしておくための水を入れる容器。水流で鮎が弱らないよう、循環機能が付いているものもあります。
- 引き舟(ヒキブネ): 釣った鮎や予備のオトリ鮎を川に入れ、曳きながら持ち運ぶための容器。移動しながら釣る際に便利です。
5. ウェーダー・ベスト・シューズ
川に立ち込んで釣りをするため、適切な服装は必須です。
- ウェーダー: 防水の胴長靴。水に濡れずに川に立ち込むことができます。安全のため、底に滑り止め加工が施されたものを選びましょう。
- 友釣りベスト: 鮎釣り用のベスト。仕掛けや小物類を収納するポケットが多数ついています。浮力材が入っているものもあり、万が一の落水時に備えることができます。
- 友釣りシューズ(フェルトソール・ラジアルソール): 川底を歩くための滑りにくい靴。苔の多い場所ではフェルトソール、石の多い場所ではラジアルソールなど、場所によって使い分けますが、最初はフェルトソールが汎用性が高いでしょう。
6. その他あると便利な道具
- 根掛かり外し: 根掛かりしてしまった時の救世主!
- 針外し: 釣れた鮎から針を外すための道具。
- 目印: 水中糸の動きを目で確認するための目印。
- ハサミ、プライヤー: 糸を切ったり、針を調整したりするのに使います。
- 帽子、サングラス: 日差し対策や、偏光サングラスは水中の様子を見るのに役立ちます。
- 水分、軽食: 釣りに集中すると喉が渇いたりお腹が空いたりします。
- 日焼け止め、虫除けスプレー: 自然の中での釣りなので、対策は必須です。
これらの道具を揃えることで、快適に友釣りを楽しめます。最初は全てを最高級品で揃える必要はありません。まずは基本的な道具を揃え、釣具店の店員さんに相談しながら、自分に合ったものを見つけていくのが良いでしょう。
友釣り仕掛けの基本的なセット方法

ここでは、友釣り仕掛けの基本的なセット方法を解説します。最初は完成品を使うことを前提に、その装着方法を説明します。
1. 竿への天上糸の取り付け
購入した鮎竿の先端には、通常「リリアン」と呼ばれる繊維製のループが付いています。このリリアンに、天上糸の先端のループを「チチワ結び」などで結びつけます。
2. 仕掛けの接続
購入した完成仕掛けは、天上糸と水中糸、そしてその先にハナカン仕掛けと掛け針がセットになっています。
- 天上糸と水中糸の接続: 天上糸の末端と水中糸の始端を、それぞれのループを結ぶ形で接続します。「電車結び」や「ユニノット」など、いくつか結び方がありますが、最初は簡単な「本結び」でも良いでしょう。
- ハナカン仕掛けと水中糸の接続: 水中糸の末端に、ハナカン仕掛けの接続部を結びつけます。多くの場合、金属製のサルカン(より戻し)などが付いているので、それに結びつけます。
- 掛け針の取り付け: ハナカン仕掛けのハリスの末端に、掛け針(錨針など)を取り付けます。多くの場合、針に結びこむためのループが付いているので、そこにハリスを通し、締め込んで固定します。
3. オトリ鮎への仕掛けの装着(ここが重要!)
これが友釣りの肝とも言える部分です。
ハナカンの装着:
- オトリ鮎を優しくタオルなどで包み、暴れないようにしっかり持ちます。
- ハナカンをオトリ鮎の左右の鼻の穴を貫通させ、指で優しく押し込みます。
- ハナカンがしっかりと鼻に収まっているか確認します。
逆さ針の装着:
- ハナカン仕掛けの途中から伸びる「逆さ針」を、オトリ鮎の尻ビレの付け根(硬い部分)に優しく刺します。
- 逆さ針がしっかりと刺さっているか確認し、オトリ鮎が不自然な体勢にならないように調整します。
逆さ針が外れてしまうと、オトリ鮎がまっすぐ泳げなくなったり、仕掛けが絡まったりする原因になるため、慎重に行いましょう。
最初は、釣具店の店員さんに教えてもらったり、動画サイトなどで手順を確認したりするのがおすすめです。オトリ鮎を傷つけないよう、優しく素早く装着する練習をしましょう。
鮎の友釣りの基本的な釣り方とコツ

いよいよ実践です。友釣りの基本的な釣り方と、釣果を上げるためのコツを解説します。
1. ポイントの選び方
鮎は縄張りを持つ魚なので、良いポイントを見極めることが重要です。
- 瀬(せ): 水の流れが速く、泡立つような場所。鮎の活性が高く、良型の鮎がつきやすいポイントです。石の裏や、流れが少し緩む場所に縄張りを持つことが多いです。
- トロ: 水の流れが緩やかな場所。比較的浅く、鮎がゆっくり泳いでいることが多いです。群れ鮎が多く、追い気がない鮎もいるので、じっくり泳がせるのが効果的です。
- 淵(ふち): 水深が深く、流れの緩やかな場所。大雨の後など、鮎が避難していることがあります。
- 石の色: 鮎がよく付く石は、ツルツルしていて、少し緑がかった藻が生えていることが多いです。これは「垢(あか)」と呼ばれる鮎の餌となる藻で、この垢を食べている鮎は縄張り意識が強く、追い気があります。逆に、白っぽい石やヌルヌルした石は、鮎があまり付いていない可能性があります。
2. オトリ鮎の泳がせ方(これが友釣りの真髄!)
オトリ鮎をいかに自然に、そして効果的に泳がせるかが釣果を左右します。
- 竿の角度と糸の張り: 竿は、なるべく上向きに構え、水中糸を水面にあまり触れさせないようにします。糸を張りすぎるとオトリ鮎が不自然な動きになり、緩めすぎると流れに負けて泳がせたいポイントから外れてしまいます。常に水中糸が適度に張った状態を保つことが重要です。
- 流れに乗せて泳がせる: 基本は、川の流れにオトリ鮎を任せて自然に泳がせることです。無理に引っ張ったり、止めたりせず、あくまでオトリ鮎の自由な動きを尊重します。
- ポイントへの誘導: 狙いたいポイント(石の裏や流れのヨレなど)へ、竿の操作でオトリ鮎を誘導します。竿を少し上げる、下げる、左右に振るなどして、微調整を行います。
- 「泳がせ」と「引き泳がせ」:
- 泳がせ釣り: オトリ鮎を流れに乗せて自然に泳がせる釣り方。最も基本となる釣り方です。
- 引き泳がせ(止め泳がせ): オトリ鮎を特定の場所に止め、少しずつ上下左右に動かしながら、野鮎の縄張りを刺激する釣り方。活性の低い鮎や、狭いポイントで有効です。
- アタリの取り方: 野鮎が掛かると、竿先に「ガツン!」という衝撃が伝わったり、竿がグンと引き込まれたりします。このアタリを見逃さず、すぐに竿を立てて合わせます。
3. 掛かった鮎の取り込み方
鮎が掛かったら、慎重に、かつ素早く取り込みましょう。
- 竿を立てる: 鮎が掛かったら、すぐに竿を立てて鮎の引きを受け止めます。竿の弾力を使って鮎をコントロールします。
- 無理に引っ張らない: 強引に引っ張ると、針が外れたり、鮎が切れたりする原因になります。竿の弾力を利用し、鮎が暴れるのをいなしながら引き寄せます。
- タモ網で慎重に: 鮎をタモ網の射程圏内まで引き寄せたら、タモ網を水中に構え、鮎を網の中へ誘導するように引き入れます。鮎がタモ網に入ったら、すぐに水面から上げましょう。
- オトリ鮎の交換: 釣れた鮎が元気であれば、次のオトリ鮎として使用できます。弱ってしまった場合は、予備のオトリ鮎に交換します。
友釣りで清流の恵みを味わおう!

鮎の友釣りは、奥深い魅力と、大自然の中で時間を過ごす喜びを与えてくれる釣りです。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、何度か挑戦するうちに、きっとその面白さに夢中になることでしょう。
今回ご紹介した基本的な知識と道具、そして釣り方のコツを参考に、ぜひ鮎の友釣りに挑戦してみてください。清流の恵みを味わい、鮎との駆け引きを存分に楽しんでくださいね!